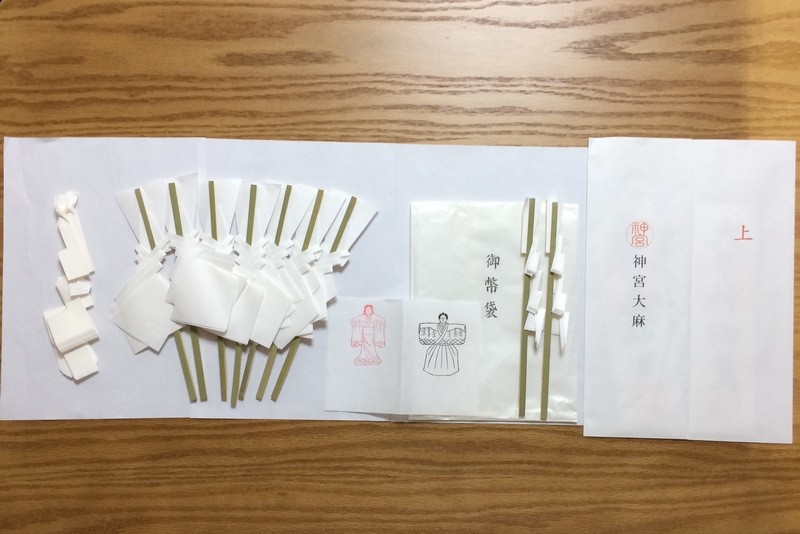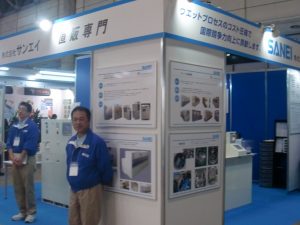President Blog
社長ブログ
2018年12月の記事一覧
年末掃除
2018年12月30日
新年を迎える準備
2018年12月22日
過去の事実を知らないことは恥ずかしい
2018年12月19日
セミコンジャパン2018年12月12-14日
2018年12月14日
展示会でお会いしましょう
2018年12月08日
ペット紹介(中等動物編)
2018年12月02日
師走です
2018年12月02日
勤労感謝の日に思う
2018年11月23日
自社でものづくりをする悦び
2018年11月18日
自社でものづくりをする大切さ
2018年11月18日
なぜ自社で装置を作ってサービスをするようになったのかを書いてみたいと思います。
勤めた会社がなくなった直後は、製造子会社も同時に整理されましたので、ものづくりをするとことが出来なくなりました。人づてに、幾つかの会社に製造もサービスもお願いして設計商社として事業を続けてきましたが、お願いした先で、お客様とトラブルになって解決できなかったことがありました。
折衝に何ヶ月も掛けて努めましたが解決せず、ご発注いただいたプロジェクトが中止になるほどのご迷惑をおかけしてしまいました。その折衝の途中で、お客様から「サンエイに発注しているのだから、サンエイが仕様通りの装置を納品してくれれば良いだけのことだ」と言っていただいたにもかかわらず。当時の自分にそこまでの自信と自覚が無く、何年も営業を掛けたにもかかわらず、発注いただいて数ヶ月後に、当方からご辞退するという失態を犯してしまったのです。自分に力が無いと人を救うことは出来ないというより、その資格が無いのだということを痛感しました。
「こういった商売をしています。」というからには、その商売に対してどんな形でも責任を取れるようにしなければならない。当たり前の話ですが、当時の私には対処する方法もチャレンジする力もなかったのです。お客様の力になりますといいつつ大変な迷惑を掛ける。私が最も軽蔑し嫌悪するようなことを私がやっていたのです。色々な協力会社様と共にお客様のために尽くすのも大切ですが、まず自分に力が無くてはならない。会社だけではなく、世の中の全てにいえることです。